認定農業者制度
認定農業者制度ってなあに?
- 将来に向かって農業でがんばっていくあなたの夢を、計画書として数字に表し将来の経営の姿をはっきりさせます
- その計画書を市町村が認定し、関係機関が具体的な支援を行い農業経営を発展させるものです
1.認定農業者制度のしくみ
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、平成5年に制定されました。効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の目標)を市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです
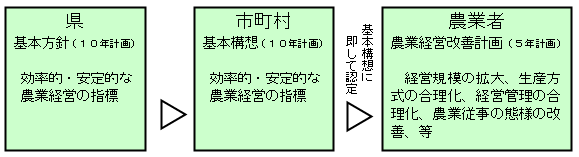
認定農業者制度は農業者自らが経営改善計画の達成のために、意欲を持って経営の改善・発展に取り組み、行政等がこれら認定農業者に対して施策を集中して支援措置を講じていくものです
認定農業者制度=経営改善に向けた自己努力を、関係機関が支援するもの
2.認定の手続き
認定を受けたい方は、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを、5年後を見通して経営改善計画を作り、市町村の窓口に提出します
計画書の作成にあたっては、市町村農業経営改善支援センターが応援しますが、自らが経営改善目標をしっかり認識することが重要です
(1)農業経営改善計画
農業経営改善計画には5年後をめざした次の4つの目標とその目標達成のための措置を記載します
- 農業経営規模の拡大(経営規模・作付内容)
- 生産方式の合理化(新技術、機械の導入による省力化等)
- 経営管理の合理化
- 農業従事の態様の改善
4項目すべてを内容とする場合もありますが、現在の経営に応じて例えば生産方式と経営管理の合理化に焦点をあてた計画になる場合もあります
(2)認定には3つの要件
経営改善計画の認定を受けるには、3つの要件を満たす必要があります
- 計画が、市町村の定める「基本構想」(経営指標等)に照らして適切であること
- 計画が達成されることが確実であること
- 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること
特に、鹿角市の「基本構想」では、
年間所得目標を「380万円以上」、年間労働時間目標を「1600時間~2000時間」と定めております
※現状として基本構想で定める目標に達していなくても、目標達成を見込める計画の策定して審議会で認められれば、認定を受けることができます。
(3)期間満了になったら再認定を
経営改善計画の有効期間は5年間とされています。計画期間満了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます
仮に、努力したにもかかわらず農産物価格の低迷等種々の事情により目標を達成できなかった場合も、再認定を受けられます。この場合、新たな計画作成にあたっては、その達成できなかった原因を明らかにし、これに対抗した目標を立てることが重要です
近年担い手の高齢化によって認定農業者数が減少が顕著となっております。
特に75歳を迎えられた方は、更新の際に後継者へ「経営継承」という形で認定を受けることも可能です
積極的にご検討ください
3.認定農業者になると
経営所得安定対策への加入
収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)
その年の対象品目の販売収入が過去の平均収入を下回った場合に、減収額の9割を補填します(対象品目:米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差によって生じる不利な部分を補正するため、担い手の生産コストのうち、販売収入では賄えない部分を補填します。
(対象品目:麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)
青色申告実施者は、上記の交付金を準備金(将来見込まれる多額の支出や損失に備えて積み立てる金額)として積み立てた場合、積立額を必要経費算入(法人は損金算入)できます。さらに、5年以内に準備金を取り崩して農用地や農業用機械・施設等の固定資産を取得した場合は、圧縮記帳できます(実質非課税)。
農用地の利用集積への支援
- 認定農業者に農業委員会が農地を優先的にあっせんします
- 県農業公社が農地の売り渡し等を行うことにより、安心して農地を取得できます。登記手続きや税金、資金、助成金等で大きなメリットがあります
【農地保有合理化事業】
経営改善に関する相談等の実施
市町村、農業委員会に設置されている農業経営改善支援センターが経営相談・情報提供を行います。
【農業経営改善支援活動事業】
機械・施設導入への助成
戦略作物の産地拡大と担い手の育成のため、農業用施設、機械類購入、苗木購入等に対し、補助金を交付します。
【かづの農業夢プラン応援事業等】
金融対策
一般の資金に比べて長期・低利な、以下のような資金が借りられます
・農業経営基盤強化資金【通称:スーパーL資金】
・農業経営改善促進資金【通称:スーパーS資金】
・農業近代化資金
・農業改良資金
提出関係書類
認定農業者になるための農業経営改善計画認定申請書は以下からダウンロード(ExcelファイルA4横)できます。
申請を行う場合は、以下1~6の確認・記入等行ったうえで、提出してください。
01_【入力可能】農業経営改善計画申請書(鹿角市)(第12条第1項) (Excelファイル: 44.7KB)
02_個人情報の取り扱い同意書(新様式) (PDFファイル: 44.9KB)
03_農業経営改善計画申請時チェックリスト(農家用) (PDFファイル: 92.0KB)
04_記入にあたっての注意事項 (PDFファイル: 732.7KB)
05_農業経営改善計画書記入例(鹿角市) (PDFファイル: 162.4KB)
06_直近の農業用所得申告書(決算書)の写し※ご自身でご用意ください
提出方法
1.持参
2.ファックス
3.メール(nousei@city.kazuno.lg.jp)
4.インターネット(Logoフォーム)
よりご提出ください。
メールおよびインターネット(Logoフォーム)提出の場合、申請書はエクセルのまま提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします
インターネット(Logoフォーム)提出はこちらから
https://logoform.jp/form/FQi7/1415850









更新日:2026年01月26日